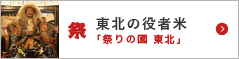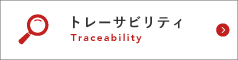人と風土が育む山形の酒米(7)


工藤吉郎兵衛翁頌徳碑(鶴岡市) 山田勢三郎翁頌徳碑(多可町にて)
幻の酒米よみがえる(3)
全国で数多くある酒造好適米品種の中で、その横綱は、と問われれば、大方の愛飲家は兵庫県産“山田錦”と答えるでしょう。それほど名をはせている山田錦は大正12年(1923)、兵庫県農事試験場で「山田穂」と「短稈渡船」を交配し、昭和11年、実に13年もの選抜・育成を経て誕生した酒造好適米品種である。爾来、今日まで酒米として君臨してきた山田錦が山形とかかわりがあることは意外と知られていない。
その一つが山田錦の母親「山田穂」である。山田穂は、明治10年頃兵庫県多可郡中町(現多可町)の山田勢三郎翁が自分の田んぼの中から優良な株を見つけ、選抜し山田穂と名付けたのがその由来と言われている。山田穂は酒造家の評判が良く、明治20年代(1887)には多可町を中心に広く普及した。その後、兵庫県農事試験場は「山田穂」の純系淘汰法によって、大正10年(1921)、11年に「新山田穂1、2号」を育成している。
前号で、山形県庄内地方の農民育種家工藤吉郎兵衛翁が酒の華と新山田穂を交配し京の華を育成したことを紹介した。翁は京の華を育成するにあたっては、はっきりとした育種上の戦略があった。それは交配親の選択である。京の華の片親の酒の華は亀の尾の血を引き、酒造好適米として折り紙のついたものである。この酒の華に西国の有名な酒造地兵庫県の代表的な酒米の新山田穂を交配したのである(菅 洋)。京の華について翁自身の筆になる来歴書はないが、新山田穂は、1号か2号かのどちらかであった。新山田穂が大正15年(1926)に酒の華と交配された時は、兵庫県で育成後、まだ4~5年しか経っていない。京の華は、山形と兵庫という、東西の酒造好適米の双方の血を受け継いだ最初の酒米品種であったと言えよう。
山田穂を創選した山田勢三郎翁の頌徳碑には「…自作田はもとより小作人にも種子を配り、あわせて近隣の農家にもわけあって栽培を勧めるとともに・・・」と刻まれている。そして工藤吉郎兵衛翁の頌徳碑にも「・・・一切オ農事ノ改良ニ捧ケ老イテ益々壮精励比ナシ而モ其ノ志ス所一己ノ利一家ノ益ニアラスシテ・・・」と刻まれている。辛苦しながら成し遂げた東西の翁に共通する原点、それは金もうけや栄誉のために品種改良をしたのでなく、酒米というイネに魅せられ、それに生涯をかけたのでないだろうか(つづく)。
2022年2月 1日 10:37